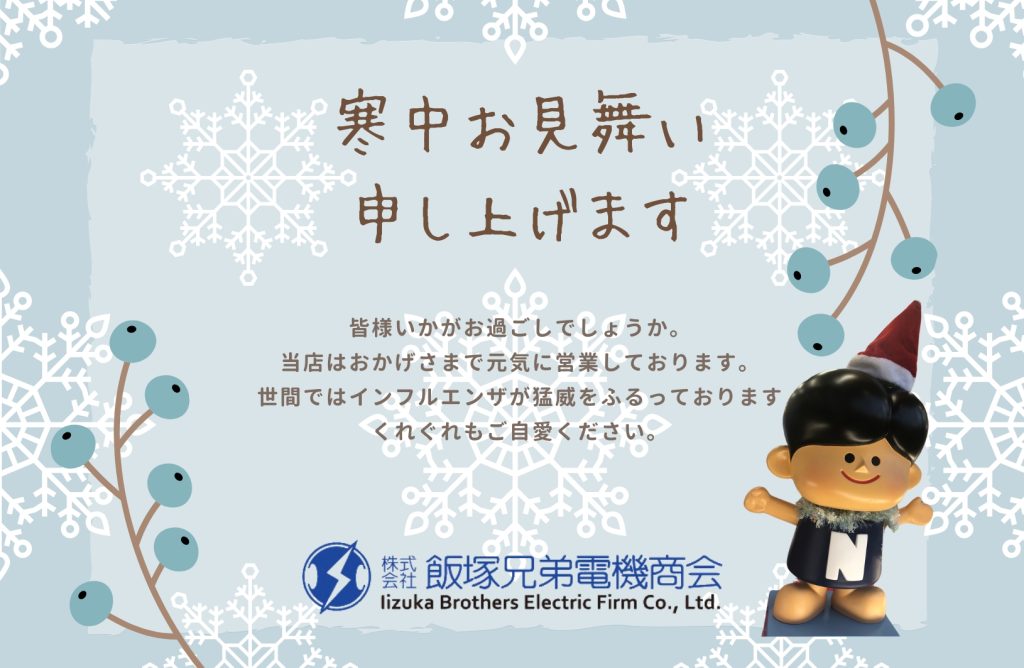
寒中お見舞い申し上げます
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 寒冷の候、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
冬本番を迎え、空気も乾燥しております。 季節柄、くれぐれもお体をご自愛ください。
本年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
令和八年 一月 飯塚兄弟電機商会
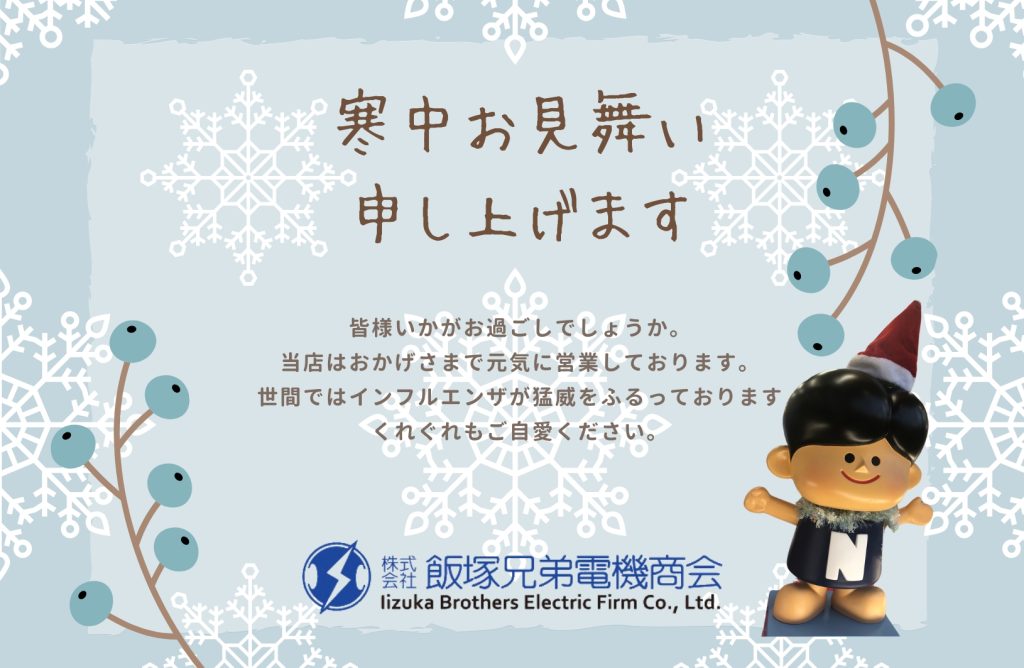
寒中お見舞い申し上げます
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 寒冷の候、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
冬本番を迎え、空気も乾燥しております。 季節柄、くれぐれもお体をご自愛ください。
本年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
令和八年 一月 飯塚兄弟電機商会

旧年中は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 皆様のおかげで、今年も無事に新しい年を迎えることができました。
私たち飯塚電機は、本年も地域の皆様の「暮らしの灯り」を守り、困ったときに真っ先に顔が浮かぶ存在でありたいと願っております。
電球ひとつのお取り替えから、最新家電による家事の時短提案、お家のリフォームまで。 皆様の毎日がより快適で、パッと明るくなるようなお手伝いを精一杯務めさせていただきます。
本年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
【年始営業のご案内】 新年は1月5日(月曜)より営業いたします。
お困りごとがございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
皆様にとって、光り輝く素晴らしい一年となりますように。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

いよいよクリスマスがやってきます。今年は「おうちでゆっくり」派の方も多いのではないでしょうか? 電気屋さんとして、プロの視点からクリスマスをより素敵にするヒントをお届けします!
私たちにできること 「クリスマスの飾り付けでコンセントが足りない!」「テレビの調子が悪い!」 そんな小さなお悩みも、街の電気屋にお任せください。フットワークの軽さは、どこにも負けません。
地域の皆様の笑顔を照らすパートナーとして、最高のクリスマスをサポートいたします!
メリー・クリスマス。
何度目かのクリスマスでも、やっぱりクリスマスは特別な日です。
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、弊社の年末年始の休業期間を下記の通りとさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
—記—

■年末年始休業期間
2025年12月30日(火)~2026年1月4日(日)
2026年1月4日(月)より通常通り営業いたします。
■お問い合わせ対応について
休業期間中にいただきました[電話、メール、FAX]によるお問い合わせにつきましては
1月4日(木)以降、順次対応させていただきます。
ご返答までに通常よりもお時間をいただく場合がございますこと、予めご了承ください。
—以上—
略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。
寒冷の候、皆様におかれましてもご多忙のことと存じますが、どうぞ良いお年をお迎えください。
敬具
いよいよ冬本番。年末年始を気持ちよく迎えるための冬支度は進んでいますか?今回は、パナソニックの家電製品を賢く活用し、暖かく、清潔で、そして快適な年末の準備を叶える方法をご紹介します。
冬の「おうち時間」の質は、暖房と空気のコンディションで決まります。年末年始に家族や友人を迎えるためにも、まずはリビングの環境を整えましょう。

パナソニックのエアコン「エオリア」は、ただ部屋を暖めるだけでなく、高性能なAIが人の居場所や活動量を分析し、ムダなく効率的に温風を届けます。最新モデルのエオリア Lシリーズなどでは、電源を入れた後の寒い時間帯を短縮する技術が進化し、朝の目覚めや帰宅時もすぐに快適な空間を提供します。
暖房の使用で気になるのが、室内の乾燥と空気の汚れです。年末は来客も増えるため、清潔な空気環境の準備は必須です。
パナソニックの加湿空気清浄機「F-VXU90」シリーズは、高濃度の「ナノイーX」を搭載。うるおいを与える加湿機能と同時に、空気中に潜む花粉、カビ菌、そして特定のウイルスを抑制します。一台で冬支度に必要な空気のケアが完了するため、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
[リンク:パナソニック 加湿空気清浄機 特集ページ]
年末の大きなタスクである料理と大掃除。パナソニックの家電製品の力を借りて、その負担を大幅に軽減し、忙しい準備期間を乗り切りましょう。
ご馳走を作る機会が増える年末。パナソニックの調理家電は、手間をかけずに本格的な味を実現し、調理時間を家族との団らんの時間に変えてくれます。
大掛かりな大掃除は年末の準備で最も負担が大きいもの。
寒い季節は、血行不良や乾燥で心身のコンディションが崩れやすいもの。年末の慌ただしさを元気に乗り切るための冬支度として、パナソニックの美容・健康家電でセルフケアを充実させましょう。
年末の疲れは、パナソニックの温感レッグリフレで癒やしましょう。疲れた足をじんわりと温めながら、エアーバッグで優しくもみほぐし、冷えやむくみを改善します。忙しい準備の合間に、自宅で手軽にリラックスできます。
[リンク:温感レッグリフレ 製品情報]
空気が乾燥する冬支度の必須アイテムが、肌の保湿ケアです。
スチーマー ナノケアは、微細な「ナノイー」スチームが肌の角質層まで浸透し、乾燥しがちな冬の肌をしっとりとうるおします。年末の来客前や、特別な日のための準備として、自宅で本格的なエステケアを。
[リンク:スチーマー ナノケア 詳細]
冬支度は、単なる寒さ対策ではありません。パナソニックの家電製品を活用することで、家事が楽になり、空気が清浄に保たれ、そして心身がリフレッシュされる。これらの年末の準備一つ一つが、皆様の暮らしを豊かにし、気持ちよく新しい年を迎える基盤となります。
ぜひこの機会に、ご自宅の環境を見直し、パナソニックと共に暖かく快適な新年を迎える冬支度を始めてみませんか。
[リンク: パナソニック製品にお問い合わせはこちらまで(当店のお問い合わせが開きます)]
師走の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2026年12月の営業日についてご案内いたします。
いよいよ今年も残すところあと1か月となりました。
12月といえば、クリスマスや大晦日、そして新しい年を迎える準備など、イベントが盛りだくさん!

慌ただしい「師走」は大切な人との楽しい予定を笑顔で過ごせたらと思います。
寒さ厳しき折ではございますが、皆様のご健康と、輝かしい新年を迎えられますよう心よりお祈り申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
冬の寒い季節、多くの家庭で気を付けたいのが「ヒートショック」です。
ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、体に負担がかかる現象のこと。特にお風呂の際、「暖かいリビング」から「寒い脱衣所」へ移動し、さらに「熱い湯船」に入るという一連の動作が、大きな温度差を生み出し、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす原因となります。
中でも最も危険な場所の一つが、冷え込みやすい「脱衣所と浴室」です。

「寒いのは我慢するしかない」と諦めていませんか? パナソニックは、このヒートショックの危険性を最小限に抑え、誰もが安全で快適に入浴できる環境を整えるための家電と住設機器を提供しています。特に、手軽に導入できる暖房家電と、根本的に空間を暖める浴室換気乾燥機が、冬の暮らしの安心に貢献します。
脱衣所と浴室の温度差をなくすことが、ヒートショック対策の基本です。しかし、脱衣所はスペースが限られており、水を使う場所のため、設置する暖房器具には安全性と速暖性が求められます。
手軽さと速暖性を重視するなら、パナソニックのセラミックファンヒーターがおすすめです。
床置きスペースがない場合は、壁に設置できる壁掛けタイプのファンヒーターも有効です。電源コードを気にせず、高い位置から温風を吹き下ろすことで、浴室への移動をより快適にサポートします。
より本格的、かつ空間全体を均一に暖めたい場合は、天井に設置する**浴室換気乾燥機(バス換気乾燥機)**が最適です。
パナソニックの浴室換気乾燥機は、「暖房」機能を使って入浴前に浴室を暖めることができます。
浴室換気乾燥機は暖房だけでなく、冬の暮らしの悩みを複合的に解決します。
冬の寒い日でも、安心して快適に入浴できる環境は、家電の力で実現できます。
手軽なセラミックファンヒーターで脱衣所の「瞬間暖房」を確保し、浴室換気乾燥機で浴室の「予備暖房」を徹底すれば、リビング、脱衣所、浴室間の温度差は大幅に軽減されます。
ヒートショックは誰の身にも起こり得る冬の危険です。この冬こそ、パナソニックの暖房家電を導入し、ご家族全員がホカホカで安心できる入浴タイムを手に入れましょう。
本記事で紹介した機能や製品は、パナソニックの以下の製品ページでご確認いただけます。
| 記事のポイント | 主な対象機種・カテゴリ | 公式サイトの参照先 |
| 脱衣所の暖房(速暖性) | セラミックファンヒーター | セラミックファンヒーター – Panasonic公式サイト |
| 脱衣所の暖房(壁掛け) | 壁掛形セラミックファンヒーター | 壁掛形セラミックファンヒーター – Panasonic公式サイト |
| 浴室の予備暖房・乾燥 | 浴室換気乾燥機(バス換気乾燥機) | [バス換気乾燥機・バス暖房 |
| ヒートショック対策 | 住まいの健康に関する情報 | ヒートショック対策 – Panasonic公式サイト |
寒い季節が到来すると、暖房効率を上げるために窓を閉めきる時間が増えます。この時期、実は室内の空気がよどみ、目に見えない「ハウスダスト」が急増しているのをご存知でしょうか。
ハウスダストの主成分は、繊維クズ、カビ、そして私たちの健康を脅かすダニの死がいやフンといった微細なアレル物質です。特に冬は、エアコンや加湿器の使用で適度な湿度が保たれ、カーペットや布団の中に潜むダニの活動が活発化しがちです。
「毎日掃除しているから大丈夫」と思っても、本当に床はキレイになっているでしょうか? 見えないからこそ対処が難しい冬のハウスダスト問題に、パナソニックの掃除機に搭載された革新的な技術『クリーンセンサー』が、確かな解決策を提示します。

従来の掃除機は、見た目のホコリが取れれば「掃除完了」でした。しかし、アレルギーの原因となる微細なハウスダストは目に見えません。
パナソニックの『クリーンセンサー』は、この「見えないゴミ」を可視化することで、掃除の常識を変えました。
クリーンセンサーは、本体部に搭載された高速赤外線センサーにより、目に見えない約20µm(マイクロメートル)の微細なハウスダストまで検知します。これは、花粉やダニのフン、死がいといったアレル物質を含むサイズです。
この視覚的なフィードバックにより、暗いベッドの下や家具の隙間など、目で見て確認しづらい場所も、ランプが青くなるまで徹底的に掃除でき、ゴミの取り残しを防ぎます。
クリーンセンサーは、単にゴミを見つけるだけでなく、冬の暮らしに欠かせない2つの大きなメリットをもたらします。
特に冬はアレルギー症状が出やすい季節です。ハウスダストが多い場所に赤ランプが点灯することで、重点的に掃除すべきエリアが一目瞭然となります。ハウスダストを徹底除去することで、冬の乾燥で悪化しがちなアレルギー症状や、喘息などのリスク低減につながります。
ゴミの量に応じてパワーを制御するため、必要以上に強い吸引力を使い続けることがありません。クリーンセンサーの表示を見ながら効率よく掃除をすることで、電力の無駄を省き、賢い省エネ掃除を実現します。
床のハウスダスト対策と同時に、パナソニックの家電で空間全体の「空気の質」を高めることが、冬の快適な暮らしには不可欠です。
掃除機で床のゴミを取り除いた後も、舞い上がったハウスダストはしばらく室内に漂います。ここで活躍するのが、「ナノイーX」搭載の空気清浄機です。
高精度なセンサーとHEPAフィルターでホコリや花粉、PM2.5をしっかり捕集。さらにナノイーXが、アレル物質やニオイを抑制し、閉めきりがちな冬の空気を徹底的にキレイに保ちます。
暖房で温かくなったカーペットや布団の奥にはダニが潜んでいます。ダニの死がいやフンを徹底的に除去するために、ふとん掃除機や、温風とたたき機能でハウスダストを浮かせて吸い込む機能を持つ掃除機を併用するのが効果的です。
特にカーペットは、掃除機をゆっくりと動かし、ノズルを密着させて毛足を起こすようにかけるのがポイントです。
ハウスダストを吸い込んだ後、ゴミ捨て時にそれが舞い散ってしまっては本末転倒です。ハウスダストが舞い散りにくい構造の紙パック式掃除機を選ぶのも一つの手です。パナソニックの紙パックは、微細な粒子を逃がさない素材を採用しており、ゴミ捨て時もクリーンな状態を保ちます。
冬のハウスダストは、目に見えない不安の種です。パナソニックの『クリーンセンサー』を搭載した掃除機は、その不安を「青いランプ」という安心に変えてくれます。
この冬、賢い家電の力を借りて、目に見えないアレル物質の脅威から家族を守り、クリーンで快適な住空間を実現しましょう。
本記事で紹介した機能や製品は、パナソニックの以下の製品ページでご確認いただけます。
| 記事のポイント | 主な対象機能 | 公式サイトの参照先 |
| 見えないゴミの検知 | クリーンセンサー搭載 掃除機 | [クリーンセンサーが決め手!見えないゴミまで逃がさない |
| ハウスダスト対策の基本 | 掃除機の選び方・対策の解説 | [ハウスダスト対策の決定版!効果的な掃除方法とおすすめ家電を解説 |
| 空気清浄機 | ナノイーX搭載 加湿空気清浄機 | 加湿空気清浄機 – Panasonic公式サイト |
| 紙パック | 紙パックの機能と選び方 | 花粉やハウスダストを逃さない!掃除機の紙パック選び – Panasonic Store Plus |
寒さが厳しくなり、暖かい部屋で過ごす時間が増える冬。日々の献立は、鍋物や煮物といった「作り置き」できる料理が増え、年末年始に向けて食材を「まとめ買い」する機会も多くなります。
しかし、冬の食材保存には特有の悩みがあります。
こうした冬の食卓の「お困りごと」を解決し、新鮮な美味しさを長持ちさせながら、毎日の調理を劇的に楽にしてくれるのが、パナソニックの冷蔵庫が誇る独自の鮮度保持技術です。特に『微凍結パーシャル』と『霜つき抑制冷凍』は、忙しい冬のキッチンを支える「チート級」の機能と言えるでしょう。

冬の時短調理の最大の敵は、カチカチに凍った食材の「解凍時間」です。パナソニックの冷蔵庫の代名詞ともいえる『微凍結パーシャル』は、この悩みを根本から解消してくれます。
微凍結パーシャルは、肉や魚が凍り始めるギリギリの温度**「約-3℃」**で保存する技術です。食材の表面だけを素早く微細に凍結させることで、以下のようなメリットが生まれます。
冬の間に増える大根や白菜を使った煮物、お鍋の準備も、肉や魚のカットがすぐにできれば、調理のストレスは大きく減るでしょう。
冬は、クリスマスやお正月に向けて冷凍食品のストックが増えたり、作りすぎた煮物や余った食材を冷凍する「ホームフリージング」が増加します。しかし、ドアの開閉などで冷凍室の温度が変化すると、冷凍焼けや霜つきが発生し、食材の美味しさが損なわれてしまいます。
パナソニックの冷蔵庫(対象機種)に搭載された**『霜つき抑制冷凍(うまもり保存)』**は、この「冷凍焼け」から食材を守るための技術です。
冷凍室の上段ケースに専用のカバー(うまもりカバー)を設けることで、ドアの開閉による外気の侵入や温度変化をブロックします。さらに、ケース内の不要な湿気だけを逃がす仕組みにより、霜の原因となる水分をコントロール。
これにより、市販の冷凍ギョーザやご飯、ホームフリージングした薄切り肉なども、霜つきを抑えて約1ヶ月間、美味しさを長持ちさせることができます。冷凍したひき肉や小分けした野菜がパラパラの状態を保てるため、使いたい分だけサッと取り出せるのも嬉しいポイントです。
冬の食卓を支える「作り置き」と「まとめ買い」は、工夫次第で調理時間の短縮と食費の節約につながります。
パナソニックの冷蔵庫は、食材を「新鮮なまま長く保存する」ことと、「使いたい時にすぐに使える」という調理の利便性を両立させることで、忙しい現代人の冬の暮らしをパワフルにサポートします。
「微凍結パーシャル」で解凍の待ち時間をなくし、「霜つき抑制冷凍」で食材のストックも安心。この冬は、パナソニックの冷蔵庫を活用して、ストレスフリーで美味しい食卓を実現してみませんか。
本記事で紹介した機能や製品は、パナソニックの以下の製品ページでご確認いただけます。最新の機種、シリーズ、詳細な機能比較は公式サイトをご覧ください。
| 記事のポイント | 主な対象機能 | 公式サイトの参照先 |
| 解凍いらず・時短調理 | 微凍結パーシャル | サクッと切れる微凍結(パーシャル) – 冷蔵庫 – Panasonic |
| 霜つき・冷凍焼け対策 | 霜つき抑制冷凍(うまもり保存) | [霜つき抑制冷凍 |
| 時短・鮮度保持技術 | はやうま冷凍・はやうま冷却 | [「はやうま冷凍」「はやうま冷却」 はやうま部チャレンジレポート |
| 冷蔵庫 総合 | 最新モデルのラインナップ | 冷蔵庫 – Panasonic公式サイト |

いよいよ寒さが身に染みる暖房器具が欠かせない季節がやってきました。
しかし、冬の室内で多くの人が抱える悩みといえば、「エアコンをつけているのに、なぜか足元が寒い」という問題ではないでしょうか。暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へたまるという性質上、エアコンを稼働させても、床や足元はなかなか暖まりにくいのがこれまでの常識でした。
「暖房は我慢するもの」「足元は電気カーペットやヒーターで別に暖めるもの」と諦めてはいませんか?
その常識を覆し、寒がりなあなたを足元から優しく包み込むのが、パナソニックのルームエアコン『エオリア』の最新モデルです。進化した気流制御と最先端のAI技術によって、これまでのエアコンとは一線を画す、快適で省エネ、そして清潔な冬の暮らしを実現します。
多くのエアコンが苦手としてきた「足元の冷え」を、『エオリア』は独自の技術で克服しています。
最新のエオリアは、電源を入れるとすぐに温風を吹き出し、寒い冬でもスピーディーに部屋を暖めます。さらに、暖房の立ち上がりだけでなく、パワフルな温風を足元へしっかりと届ける独自の気流制御を採用。くつろいでいる時や、朝の着替えの時など、寒さを感じやすいタイミングでも、冷えやすい足元からしっかり暖まる心地よさを提供します。
特に、厳しい寒さの地域にお住まいの方には、極寒の環境下でも運転を実証した**寒冷地向けエアコン「フル暖エオリア」**もラインナップされており、その高い暖房能力は安心感をもたらしてくれます。
足元だけのスポット暖房や、持ち運びたい場合には、ナノイーX搭載のセラミックファンヒーターも選択肢に入ります。パワフルな温風で素早く暖めるのはもちろん、エアコンと同じく「ナノイーX」を搭載することで、暖房しながら空気の清潔性にも配慮。場所を選ばず、快適な暖かさを提供してくれます。
『エオリア』の最新モデルに搭載された「エオリアAI」は、単に温度を管理するだけでなく、あなたの暮らしと部屋の状況を深く学習し、最適な運転を実現します。
エオリアAIは、人の在・不在や、日射量、家具の位置と間取りまで、さまざまな情報を細かく感知する各種センサーを駆使します。これにより、「家族の誰がどこにいるか」「日差しで部屋が暖まりすぎないか」といった状況をリアルタイムで解析。
取得した情報をもとに、部屋にいる人全員が快適に過ごせるように運転を最適化・学習します。必要な時だけパワフルに、快適な状態になったら自動で効率の良い運転に切り替えるため、**「我慢しない快適さ」と「無駄のない省エネ」**を高いレベルで両立できるのです。
冬の暖房の悩みは寒さだけではありません。暖房運転による**「乾燥」と、窓を閉め切りがちになることによる「空気の汚れやニオイ」**も大きな問題です。パナソニックは、この課題も独自の技術で解決しています。
プレミアムモデルであるLXシリーズなどには、給水の手間がいらない**「加湿・換気機能」**が搭載されています。室外機から外気の水分を取り込み、室内にうるおいを届ける仕組みです。
これにより、暖房運転中でも給水タンクに水を足す手間なく、部屋の湿度を快適に保つことができます。乾燥による肌や喉の不快感を抑え、インフルエンザなどが流行する時期のウイルス対策にもつながります。
さらに、パナソニック独自の微粒子イオン技術**「ナノイーX」**を搭載。空気中の水分を凝縮して生成されるナノイーXは、従来のナノイーの10倍の量の高反応成分(OHラジカル)を含んでおり、以下のような効果が期待できます。
暖房運転中だけでなく、暖房を使わない季節でも、ナノイーXを放出することで一年中部屋の空気を清潔に保つことができるのです。
「エアコンは足元が冷える」という先入観を捨てて、パナソニックの『エオリア』を導入すれば、この冬の暮らしは劇的に変わるでしょう。パワフルな暖房性能、賢いAI制御、そして清潔・うるおい機能が一体となり、あなたとご家族に最高水準の快適空間を提供します。
この冬こそ、我慢の暖房から卒業し、足元から暖まる心地よい暮らしを始めてみませんか。
本記事で紹介した機能や製品は、パナソニックの以下の製品ページでご確認いただけます。最新の機種、シリーズ、詳細な機能比較は公式サイトをご覧ください。
| 記事のポイント | 主な対象機種・カテゴリ | 公式サイトの参照先 |
| エアコン「エオリア」総合サイト | ルームエアコン | エアコン(エオリア) – Panasonic公式サイト |
| 足元暖房・快適設定 | 暖房に関する特集ページ | [冬のエアコン暖房の設定温度の目安は? |
| 加湿・換気機能(LXシリーズ等) | ハイグレードモデル LXシリーズ | エオリア 2025年モデル LXシリーズ(または最新の加湿機能搭載シリーズ) |
| 寒冷地向けエアコン | フル暖エオリア UXシリーズなど | フル暖エオリア 2025年モデル UXシリーズ |
| ナノイーX搭載暖房器具 | ファンヒーター、電気カーペットなど | 電気カーペット(ホットカーペット)・暖房器具 – Panasonic公式サイト |